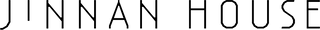エンパワーメント=本来持っている力を湧き出させること
陶芸家・野口悦士さんが創り出すうつわには、そこに据えられた万物をエンパワーメントする力があります。陶芸を志して種子島に渡り、アメリカ・デンマークなどでの滞在制作を経て、現在は鹿児島を拠点に活動する野口さん。『物静かで力強い、プリミティブでモダン。』そう謳われる作品たちのルーツ、インスピレーションの源について、今回は特別にお話しを伺うことができました。
 Courtesy of Etsuji Noguchi
Courtesy of Etsuji Noguchi
手仕事への憧れ、陶芸との出会い
茅ヶ崎の波乗りだった野口さんが陶芸に目覚め、種子島に渡ったのが約22年前のこと。そのもう少し前、サーフィン好きが高じて野口さんは茅ヶ崎のサーフボード工場でボード作りのアルバイトをしていました。そこで働く先輩たちの働きっぷりは気ままなもので、どんなに仕事が忙しくても波がいいと昼間から海に行ってしまうほど。そんなある意味、ワークライフバランスの取れた仕事に憧れ「手仕事」に興味を持つようになったといいます。
何年かのアルバイトの末、このままここで働こう!と決意するものの、ボード作りは粉塵対策で重装備のマスクをしながら作業することも。人間関係も仕事内容も大好きで満足のいくものだったのですが、健康面のことを考えてほかの事にもチャレンジすることにしました。その一つが「陶芸」だったのです。
 Courtesy of Etsuji Noguchi
Courtesy of Etsuji Noguchi
場所を超えた師匠と呼べる存在
図書館でたまたま見た本に載っていたある陶芸作品。力強くて呼ばれているような気がして、なんの知識もなかったものの、その作者がいるという種子島に行くことにしました。それはのちに、師匠となる陶芸家・中里 隆さんの作品でした。中里さんは、唐津焼の人間国宝・中里 無庵さんの家に生まれ、現代の唐津焼作家を代表する一人です。そんな中里さんを追い種子島に行ったものの、もう本人はいないというハプニングが発生。なにもかもが行き当たりばったりでしたが、野口さんはそんなに深くを考えていなかったと言います。
「まあ、種子島ならサーフィンできるしと、後先考えずにいましたね。焼き物のことを何も知らず言ったので最初のうちは薪割りとか草払いとかしながら、独学で土を練る練習などをしていました。」
 Courtesy of Etsuji Noguchi
Courtesy of Etsuji Noguchi
種子島に渡り、独学で陶芸を初めて約3年。野口さんは中里さんに教えを請いたいとついに手紙を書きます。
「中里先生は、お返事を電話でくださったのですが、『弟子は取らない』と断られてしまってがっくりでした。けど一度僕のいる唐津まで遊びにきてみたら?って誘ってくれたんです。」
すぐさま唐津を訪れた野口さん。感動もひとしお、ここでは自分は勉強できないのかと打ちひしがれました。唐津から種子島に戻ってきてからは、また独学で作陶を続けました。そうしているうちに中里先生が古希記念の展覧会を開くから縁のある種子島でつくりたいと、声をかけてくれたといいます。中里先生が種子島にいた約1週間ほど、全力でサポートし様々なことを学び取る中で、ゆっくりと堅実に掴み取った縁。中里先生がアメリカに作品づくりに行く時には弟子として連れて行ってくれるまでに。年に1回、2ヶ月ほどの滞在を何度か、中里さんと過ごしたアメリカでの日々は今の野口さんの作品づくりに深く関わっています。
 Courtesy of Etsuji Noguchi
Courtesy of Etsuji Noguchi
「中里先生はアメリカに行く時、小さいキャリーケースに自分の荷物をいれて、大きなボストンバッグに昆布とか味噌とかなかなか手に入れられないものをパンパンに詰めて和食を作れるようにしていたんです。アメリカで出会った人もフランクに招いて作ったうつわでふるまったり。朝ごはんの時の話題は昼ごはんの話で、『魚は僕がさばくから野口くんは野菜を干しておいてね。』と、仕込みの合間に作陶をするような生活でした。」
決してうつわが中心ではなく、営みの中にあるものとして輝くもの。野口さんにとって大切なことの優先順位が経験をもって見えた出来事でした。
デンマークとうつわへの可能性
2019年には、オランダのヴァールリバーという川の土手で取れる粘土を何か価値あるものに変える、というプロジェクトで、2ヶ月滞在制作をしたりと活躍の幅を広げる野口さん。採ってきた粘土を精製して焼きしめるという工程は種子島の経験がとても役に立ったそう。
その後、アーティストインレジデンスを通じて40歳の時、初めてデンマークをおとずれます。かねてから熱望していたKH Würtz(コーホーヴューツ)への訪問。ここは世界的イノベーティブレストランを牽引するコペンハーゲンの「noma」などのうつわを手がけるアトリエです。父と息子を中心とした少人数の体制のアトリエ。アシスタントも合わせて7〜8人ほどが世界中のレストランからの注文に真摯に向き合っている様子に「こんな世界がデンマークにもあるんだ!」と刺激を受け心がぴったりとハマっていきました。そして今まで見てこなかった土や釉薬の使い方を学び、表現の可能性を感じます。
 Courtesy of Etsuji Noguchi
Courtesy of Etsuji Noguchi
後ろにあるもの、前にあるもの
中里さんから得たプリミティブな技法、KH Würtzから得たモダンな発想、野口さん自身も2人のハイブリッドと冗談まじりに話すほど、双方からの経験が混ざり合い、今の野口さんの作品をつくっています。奇跡のような縁を掴み取る行動力とエネルギー、そして得たものを丁寧に咀嚼し自分の作品に落とし込む技、そのすべてが魔法となって現在の野口さんのうつわの魅力となっているのでしょう。
現在、多くの日本を代表するレストランでは、野口さんのうつわが麗しき料理たちをライトアップしています。nomaにとってKH Würtzがあるように、日本のフードカルチャー界に野口さんのうつわは欠かせないものとなっているはずです。野口さんのこれまでを知ると、作品に対する眼差しもまた違ったものになるでしょう。ぜひ手元にお迎えしてその味わいを楽しんでみてくださいね。

さいごに・・・
JINNAN HOUSE で扱う、野口さんの作品の数々。
ご本人よりそれぞれのポイントを伺いました。
『緑青(ろくしょう)』


始まりはやはり種子島時代に、大きな薪の窯をせっせと焚いていた若い頃、
薪を投げ込む場所の近くにあったものが、灰の中に埋まっているような状態で
窯出しされたものが、とても魅力的な色と質感だったものを再現しようとしているものです。現在は長く焼くのではなく、最低でも4回以上、何度も繰り返し焼くことによってあの色と質感を得ていますが、何度焼けばいいのか、またどんな仕上がりになるのかはいまだに全然わかりません。
『灰白(かいはく)』


白は白土の白化粧の白、黒と赤は土からの発色で、黒は還元焼成、赤は酸化焼成によるものです。こちらはハガキシリーズで、たまたま届いた葉書にインスピレーションを受けました。和菓子をひとつポンとのせてみてください。
『焼きしめ』


種子島の時から今までずっと続けている技法です、
土そのものを釉薬をかけずに焼き締めた、原始的な焼き物で、
そのために土の選択が大事です、
最初は少しザラザラした質感ですが、使い込んでいくと
しっとりつややか、色味も深くなっていく、
育つうつわの代表だと思います。
『白釉』

デンマークで見た、あくまで心象風景ですが、
なんとなく、雪に朝露が滴って少し解けたような?
雪が少し溶けて地面が見え隠れするような?
そんなイメージです。
野口悦士
1975年、埼玉県生まれ。 陶芸を志して種子島に渡り、2006年より中里 隆氏に師事。 2018年にデンマークのKH Würtzにて薪窯築窯。アメリカ・デンマークなどでの滞在制作を経て、現在は鹿児島に拠点を置く。
Photo by Taro Oota
Text by Ami Yamazaki